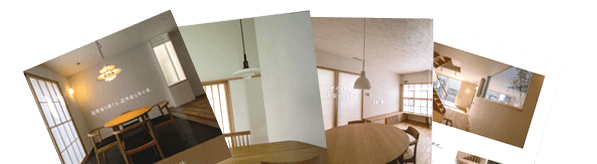- 代表ブログ
本物の大工は絶滅危惧種──職人の背中が消えていく前に

今から40年以上前私が大工の世界に入った頃は、大工が柱を一本一本刻み、墨付けをして、現場で木を組んでいました。現代の家では見れない伝統的な木の継手(※)を墨付けて加工していました。今では、神社仏閣でしかそのような継手は見れません。木の癖を見抜き、天気で木の動きを読み、手の感覚だけで“ミリ”を調整する。そんな大工が家を「建てて」いたのです。
しかし、現代の大工仕事は「家を組み立てる」が主流になっています。
(※継手…短い木材同士を繋ぎ合わせて、必要な長さや強度を持った木材にするための技術)
現代の建築はプレカットと大量生産が主流
住まいの建築は30年以上前から、プレカット工場で機械が木材を加工し、現場ではそれをマニュアル通りに組み立てる流れになりました。その結果、技術ではなく手順が重視され、経験よりも効率が優先される時代が主流となったのです。今後、大工の伝統的な技術は衰退していくでしょう。
もちろん、現代の建築にも良さはあります。スピード、コスト、均一な品質。しかし、その一方で「手仕事の家」がどんどん姿を消しているのも事実です。大工という言葉の重みも、薄れてきてはいないでしょうか。
本物の大工とは何か?
本物の大工とは、単なる作業員ではありません。木を読む力、設計図を超えた応用力、そして何より「家族が暮らす場を造る」という意識を持った職人です。
木が割れる音、ノミを打つ手のリズム、現場に流れる独特の緊張感──それらすべてを背負って、家を造る。そんな大工は、今や絶滅危惧種となりつつあります。
大工就業者数の推移
総務省「国勢調査」によると、木造住宅の担い手である国内の大工就業者数は以下のように推移しています。
| 1985年 | 約80万人 |
| 2000年 | 約54万人 |
| 2010年 | 約40万人 |
| 2020年 | 約30万人 |
※参考:大工就業者の推移|国土交通省
この35年間で、約50万人もの大工が減少しました。特に、若年層の就業者数が少なく、60歳以上の高齢者が大工全体の約3割を占めており、今後の担い手不足が懸念されています。
技術は受け継がれるのか?
問題は、大工の後継者不足です。若い人が大工にならない。なっても、すぐ辞めてしまう。「キツい・汚い・危険」の3Kで片付けられ、魅力が伝わっていないのが現状です。
しかし、本物の大工仕事には、数字では測れない「誇り」があります。家が完成し、お客様の笑顔を見たときの達成感。それは、どんな現代的な仕事でも得がたいものです。
だからこそ、本物の大工の仕事を残したい
「本物の大工」の仕事が残る現場は、もはや数えるほどしかありません。それでも、残っている。木造建築の良さを知り、伝統の技を継ごうとしている若者も、わずかながらいます。だからこそ、声を上げたい。
本物の大工は絶滅危惧種かもしれません。でも、ゼロにはしたくない。そんな気持ちから、弊社では、大工さんを社員雇用しています。
私も元大工職人、常務も大工職人でした。若い大工さんがいなくて困っている工務店が多い中、大変有難いことに、弊社では40代・30代・20代・10代の大工さんが働いてくれています。私や常務が経験してきた事を伝えていきたいと思います。
そして、彼らも習得した技術を伝承してくれたら有難いです。
大工という職業は、単なる技術職ではなく、日本の文化や暮らしを支えてきた重要な存在です。その価値を再認識し、次世代へと繋げていくことが求められています。